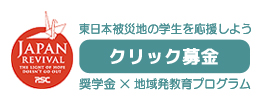гГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБЃйБФдЇЇ
дїКеЫЮгБѓгГИгВ§гГђгГїгГ°гГ≥гГЖгГКгГ≥гВєгБЃи©±гБІгБЩгБЃгБІгАБгБКй£ЯдЇЛдЄ≠гБЃжЦєгБѓгБФж≥®жДПгБПгБ†гБХгБДгБЊгБЫгАВ
гБЯгБ†гБЧгАБжШ†еГПгБѓгВ§гГ©гВєгГИгБ®гВ§гГ°гГЉгВЄзФїеГПгБ†гБСгБЂгБЧгБЊгБЩгБЃгБІгАБеЃЙењГгБЧгБ¶гБФи¶ІгБПгБ†гБХгБДгАВ

гБХгБ¶гАБгВњгВ§гГИгГЂгБЃгАОгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгАПгБ®гБѓдљХгБЛгБ®гБДгБДгБЊгБЩгБ®гАБе∞СгБЧеЙНгБЂ twitter гБІ
гГ™гГДгВ§гГЉгГИгБХгВМгБЊгБПгБ£гБЯдЄЛгБЃзФїеГПгАБгАОйЫїиїКгБЃйБФдЇЇгАП гВТи¶ЪгБИгБ¶гБКгВЙгВМгБЊгБЩгБЛгАВ
гБЭгБЖгАБгГИгВ§гГђгБЃгГДгГЮгГ™гВТиІ£жґИгБЩгВЛгАБгБВгБЃйБУеЕЈгБЃгБУгБ®гБ™гВУгБІгБЩгАВпЉИж≥®1пЉЙ

гБЊгБВгАБгБУгБЃзФїеГПгБѓжЦ∞еУБгВТдљњгБ£гБ¶гБДгВЛгБ®дњ°гБШгБЯгБДгАБгБ®гБДгБЖгБЛгАБжШОгВЙгБЛгБЂгГНгВњгБ†гБ®
жАЭгБДгБЊгБЩгБМгАБгБУгБЃйБУеЕЈгАБгВ§гВґгБ®гБДгБЖгБ®гБНе§Іе§ЙйЗНеЃЭгБЧгБЊгБЩпЉИйЫїиїКгБІгБѓдљњгВПгБ™гБДпЉЙгАВ
гБ®гБДгБЖгБЃгВВгАБжЬАињСгАБеЃЯеЃґгБЃгГИгВ§гГђгБІжѓНгБМгГИгВ§гГђгГГгГИгГЪгГЉгГСгГЉгВТгВИгБПдљњгБЖгБЫгБДгБЛгАБ
жЩВгАЕгАБгГИгВ§гГђпЉИжіЛеЉПпЉЙгБМгБ§гБЊгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгАБжХ∞еЫЮ詶гБЧгБ¶гБДгВЛгБЖгБ°гБЂгАБгБУгБЃйБУеЕЈгВТдљњгБЖ
гВєгВ≠гГЂгБМгБЩгБ£гБЛгВКиЇЂгБЂгБ§гБНгБЊгБЧгБЯгБЃгБІгАБдїКеЫЮгАБгБЭгВМгВТгБЊгБ®гВБгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ
![]()
жіЛеЉПгГИгВ§гГђгБЃе†іеРИ
гАОжіЛеЉПгАПгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧпЉИе§ІпЉЙгБМ
дљњгБДгВДгБЩгБДгАВ
гБЯгБ†гБЧгАБдЊњеЩ®гБЃе§ІгБНгБХгБЂгВИгВЛгАВ
еЄВи≤©гБХгВМгБ¶гБДгВЛгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБѓгАБжЩЃйАЪгБЃгВЂгГГгГЧеЮЛгБЃгГҐгГОгБ®гАБгВЂгГГгГЧгБЃеЕИгБМзЛ≠гБЊгВКеЗЇгБ£еЉµгВКгБМ
гБВгВЛгГҐгГОпЉИгАОжіЛеЉПгАПпЉЙгБЃпЉТз®Ѓй°ЮгБМгБВгВКгАБеЗЇгБ£еЉµгВКгБМгБВгВЛгГҐгГОгБѓе§ІгБ®е∞ПгБЂеИЖгБЛгВМгБ¶гБДгВЛгВИгБЖгБІгБЩгАВ
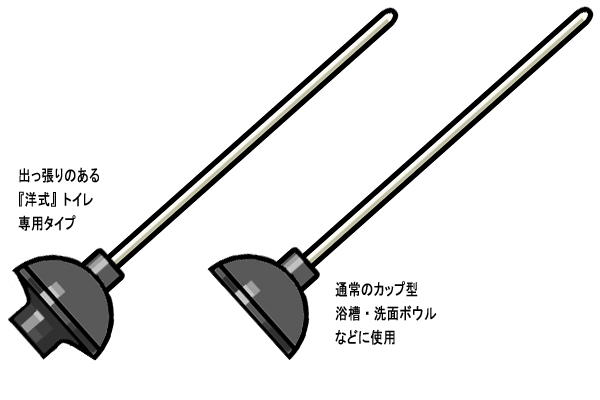
дЄАиИђзЪДгБ™жіЛеЉПгБЃж∞іжіЧдЊњеЩ®гБѓгАБж∞ігБЃжµБгВМеЗЇгВЛйГ®еИЖгБМи§ЗйЫСгБ™ељҐгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБгВЂгГГгГЧеЮЛ
гБІгБѓгАБеЃМеЕ®гБЂгВЈгГЉгГЂгГЙгБІгБНгБ™гБДгБЃгБІгАБгАОжіЛеЉПгАПпЉИе§ІпЉЙгБМгБДгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВгБЯгБ†гБЧгАБжіЛеЉПдЊњеЩ®гБІ
е∞ПеЮЛгБЃгВњгВ§гГЧгБМгБВгВКгАБгАОжіЛеЉПгАПпЉИе§ІпЉЙгБІгБѓеЗЇгБ£еЉµгВКйГ®еИЖгБМжМњеЕ•гБІгБНгБ™гБДе†іеРИгБМгБВгВКгБЊгБЩгБЃгБІгАБ
жОТж∞іеП£гБЃеЊДгВТи®ИгБ£гБ¶гАБи≥ЉеЕ•гБЩгВЛжЦєгБМгВИгБДгБІгБЧгВЗгБЖгАВ
![]()
гГДгГЮгГ™гБЃеАЛжЙАгБѓжДПе§ЦгБЂињСгБДгАВ
ж∞іжіЧгГИгВ§гГђгБЃгБЧгБПгБњгВТзРЖиІ£гБЧгБ¶
гГДгГЮгГ™гБМиІ£жґИгБЧгБ¶гБДгБП
гВ§гГ°гГЉгВЄгВТгГПгГГгВ≠гГ™гБХгБЫгВЛгАВ
ж∞іеЫЮгВКгБЃж•≠иАЕгБХгВУгБЃи©±гБІгБѓгАБ¬†дЊњеЩ®гБЛгВЙдЉЄгБ≥гБ¶дЄЛж∞ізЃ°гБЂйАЪгБШгВЛжОТж∞ігГСгВ§гГЧгБЃйАФдЄ≠гБІгАБгГДгГЮгГ™гБМ
зЩЇзФЯгБЩгВЛгБУгБ®гБѓгБВгБЊгВКгБ™гБПгАБгГДгГЮгГ™гБЃгБїгБ®гВУгБ©гБѓгАБдЊњеЩ®еЖЕйГ®гБЃжЫ≤гБМгБ£гБЯеАЛжЙАгБЃж∞іиЈѓгБІиµЈгБУгБ£гБ¶
гБДгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВ
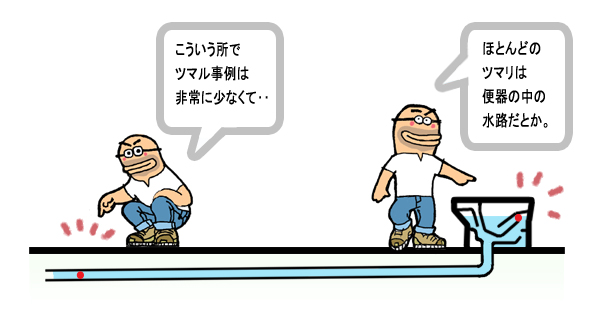
дЊњеЩ®гБЃжЦ≠йЭҐгВТи¶ЛгВЛгБ®гАБгБДгВНгБДгВНгБ™з®Ѓй°ЮгБМгБВгВЛгБУгБ®гБМгВПгБЛгВКгБЊгБЩгБМгАБгБЭгВМгБІгВВгАБгБЩгБєгБ¶еЕ±йАЪгБЧгБ¶
гБДгВЛгБЃгБѓгАБж∞іиЈѓгБМеЗДгБДжА•гВЂгГЉгГЦгБІжЫ≤гБМгВКгБПгБ≠гБ£гБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБІгБЩгАВ
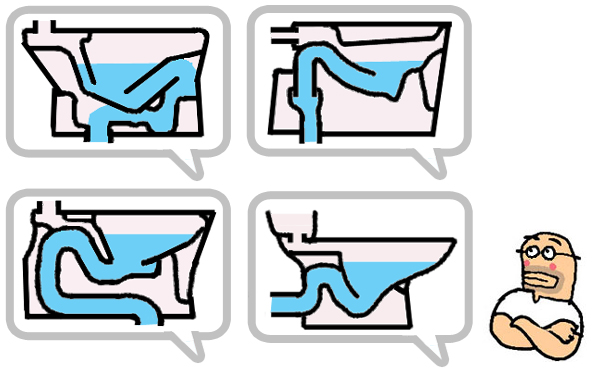
гБУгВМгБШгВГгБВгАБгГДгГЮгГ™гВДгБЩгБДгВПгБСгБ†пЉБгБ®гАБжАЭгБ£гБ¶гБЧгБЊгБДгБЊгБЩгБМгАБгБУгБЃжЫ≤гБМгБ£гБЯж∞іиЈѓгБЂгБѓгАБпЉТгБ§гБЃ
жЈ±гБДзРЖзФ±гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБЭгБЃвС†жОТж∞ігГИгГ©гГГгГЧгАВдЄЛж∞ізЃ°гБЛгВЙгБЃиЗ≠гБДгВДз°ЂеМЦж∞ізі†гАБгБЊгБЯеЃ≥иЩЂгБМж∞іиЈѓгБЛгВЙйАЖжµБгБЧгБ¶гБПгВЛгБЃгВТ
йШ≤гБРгБЯгВБгАБгБУгБЃжЫ≤гБМгБ£гБЯеАЛжЙАгБІеЄЄгБЂж∞ігВТжЇЬгВБгАБйАЪж∞ЧгВТйБЃжЦ≠гБЩгВЛжІЛйА†гБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБУгВМгВТ
е∞Бж∞іпЉИгБµгБЖгБЩгБДпЉЙгБ®еСЉгБ≥гБЊгБЩгАВгБУгВМгБѓгАБгВ≠гГГгГБгГ≥гВЈгГ≥гВѓгВДжіЧйЭҐгГЬгВ¶гГЂгБЃйЕНзЃ°гБЂгВВи¶ЛгВЙгВМгБЊгБЩгАВ
гБЭгБЃвС°гВµгВ§гГЫгГ≥жІЛйА†гАВдЊњеЩ®еЖЕгБЃж∞ігБ®дЄЛж∞ізЃ°гБЃйЂШгБХгВТжѓФгБєгВЛгБ®гАБдЄЛж∞ізЃ°гБЃжЦєгБМдљОгБПгАБдЄ°иАЕгБМ
ж∞ігБІжЇАгБЯгБХгВМгБЯгГСгВ§гГЧгБІгБ§гБ™гБМгВЛгБ®гАБдЊњеЩ®еЖЕгБЃж∞ігБѓеЗДгБДеЛҐгБДгБІеРЄгБДеЗЇгБХгВМгБЊгБЩгАВгБУгВМгБМгАБ
гВµгВ§гГЫгГ≥гБЃеОЯзРЖгВТењЬзФ®гБЧгБЯж∞іжіЧгГИгВ§гГђгБІгАБгБУгБЃжОТж∞іеКЫгБѓйЭЮеЄЄгБЂеЉЈгБПгАБгБДгБ£гБЯгВУгГИгГ©гГГгГЧгБЃ
е∞Бж∞ігВВеРЂгВБгБ¶гБЩгБєгБ¶еРЄгБДеЗЇгБХгВМгБЊгБЩгАВгБУгБУгБІе∞Бж∞ігБМз†ігВЙгВМпЉИз†іе∞БпЉЙгАБйАЪж∞ЧгБЧгБ¶гБЧгБЊгБДгБЊгБЩ
пЉИж∞іжіЧгГИгВ§гГђгБІж∞ігВТжµБгБЧгБЯжЩВгБЃе§ІгБНгБ™йЯ≥гБѓгБУгБУгБІзЩЇзФЯгБЧгБЊгБЩпЉЙгБМгАБгБЭгБЃеЊМгАБгВњгГ≥гВѓгБЃж∞ігБМ
жµБгВМгБ¶гАБеЖНгБ≥гГИгГ©гГГгГЧгВТжЇАгБЯгБЧгБЊгБЩгАВгБУгБЖгБЧгБ¶ж±Ъж∞ігБМдЊњеЩ®еЖЕгБЂжЃЛгВЛгБУгБ®гБ™гБПгАБе∞Бж∞ігБМеЄЄгБЂ
жЦ∞гБЧгБДж∞ігБЂеЕ•гВМжЫњгВПгВЛжІЛйА†гБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гГДгГЮгГ™гБѓгАБгБУгБЃгГИгГ©гГГгГЧгБЃеЕИгАБж∞ігБМжЇАгБЯгБХгВМгВДгБЩгБДгВИгБЖгБЂжЫ≤гБМгБ£гБЯдЄКжШЗзЃ°гБМдЄЛи°МзЃ°гБ®
гБ§гБ™гБМгВЛеАЛжЙАгБІиµЈгБУгВКгВДгБЩгБПгАБгБУгБУгБЂгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБЃж∞іеЬІгБЂгВИгВЛжМѓеЛХгВТдЄОгБИгБ¶гАБгГДгГЮгГ™гВТ
гБїгБРгБЧгБ¶гАБж∞ігБЃжµБгВМгВТеЖНгБ≥дљЬгВКеЗЇгБЩгВИгБЖгБЂгБЩгВЛгВПгБСгБ™гБЃгБІгБЩгАВ
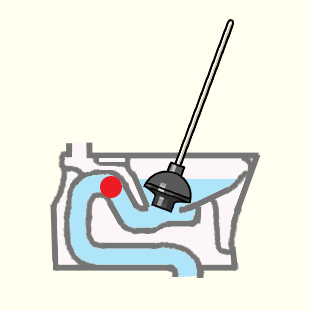
![]()
дљЬж•≠гВТеІЛгВБгВЛеЙНгБЂгАБгБЊгБЪгАБ
вС†ж±Ъж∞ігБМдЊњеЩ®гБЛгВЙгБВгБµгВМгВЛгБУгБ®
вС°дљЬж•≠дЄ≠гАБж±Ъж∞ігБМгГПгГНгВЛгБУгБ®
гБЄгБЃгАБжЇЦеВЩгВТгБЩгВЛгАВ
дЊњеЩ®гБЃж∞ійЭҐињСгБПгБЊгБІж∞ідљНгБМгБВгВЛзКґжЕЛгБІгАБгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгВТжКЉгБЧиЊЉгВАгБ®гАБгВњгГ≥гВѓгБЃжОТж∞іеЉБгБМйЦЛгБДгБ¶гАБ
гВњгГ≥гВѓгБЃж∞ігБМгБХгВЙгБЂжµБгВМиЊЉгБњгАБж±Ъж∞ігБМгГИгВ§гГђгБЃеЇКгБЂжЇҐгВМгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБЭгВМгБЂеВЩгБИгБ¶гАБгГИгВ§гГђгБЃеЇКгБЂгБВгВЛгАБгГИгВ§гГђгГЮгГГгГИгАБгВєгГ™гГГгГСгАБгГИгВ§гГђгГГгГИгГЪгГЉгГСгГЉгАБеРДз®ЃжґИиЗ≠еЙ§гБ™гБ©гБѓгАБ
гБДгБ£гБЯгВУгАБйААйБњгБХгБЫгБ¶гБКгБНгБЊгБЩгАВгБІгБНгВМгБ∞гАБйХЈйЭігВДеП§гБДйБЛеЛХйЭігБ™гБ©гВТ展гБДгБ¶дљЬж•≠гБЧгБЯгБїгБЖгБМгАБ
иґ≥гБМжњ°гВМгВЛењГйЕНгВТгБЫгБЪгБЂгАБиЕ∞гВТеЕ•гВМгБ¶дљЬж•≠гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ
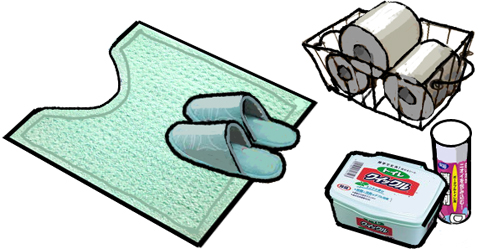
гБЊгБЯгАБдљЬж•≠дЄ≠гБѓж±Ъж∞ігБМгГПгГНгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгБЃгБІгАБ45гГ™гГГгГИгГЂдї•дЄКгБЃе§ІгБНгБ™йАПжШОгБЃгГУгГЛгГЉгГЂпЉИгВігГЯпЉЙиҐЛгВТ
жХ∞жЮЪзФ®жДПгБЧгАБгБЭгБЃдЄАгБ§гВТеИЗгБ£гБ¶е±ХйЦЛгБЧгБ¶еє≥йЭҐгБЂгБЧгАБдЄ≠е§ЃгБЂз©ігВТгБВгБСгБ¶гГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгВТйАЪгБЧгБ¶дљЬж•≠гБЩгВЛгБ®гАБ
гГПгГНгБМгБВгВЛз®ЛеЇ¶йШ≤гБТгБЊгБЩгАВгГУгГЛгГЉгГЂиҐЛгБѓгАБжњ°гВМгБ¶гБЧгБЊгБ£гБЯгГИгВ§гГђгГЮгГГгГИгБ™гБ©гВТеЕ•гВМгБЯгВКгАБгБЩгБ£гБЛгВКжњ°гВМгБ¶
гБЧгБЊгБЖз©ігВТйЦЛгБСгБЯгГУгГЛгГЉгГЂгВДгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧиЗ™дљУгВТзЙЗдїШгБСгВЛе†іеРИгБЂгВВйЗНеЃЭгБЧгБЊгБЩгАВ
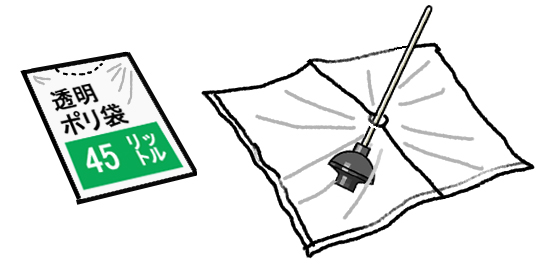
![]()
2пљЮ3еЫЮгБІйАЪгБШгВЛгБ®жАЭгБЖгБ™гАВ
гВ∞гГГгБ®жКЉгБЧгБ¶гАБгГЭгГ≥гБ®еЉХгБПгАБ
гВ∞гГГгБ®жКЉгБЧгБ¶гАБгГЭгГ≥гБ®еЉХгБПгАБгВТ
гГ™гВЇгГЯгВЂгГЂгБЂзє∞гВКињФгБЧгАБ
гГДгГЮгГ™гВТгБїгБРгБЩгВ§гГ°гГЉгВЄгБІ
ж∞іеЫЮгВКгБЃж•≠иАЕгБХгВУгВТеСЉгВУгБІдљЬж•≠гБЧгБ¶гВВгВЙгБЖе†іеРИгБІгВВгАБгБЯгБДгБ¶гБДгБѓгАБгБУгБЃгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБЛгВЙ
詶гБХгВМгБЊгБЩгАВгБЭгВМгБІгАБйАЪгБШгБ¶гБЧгБЊгБИгБ∞гАБгБ≤гБ®еЃЙењГгБІгБЩгБМгАБгБ™гВУгБЛжВФгБЧгБДгБШгВГгБ™гБДгБІгБЩгБЛгАВ
гБЭгВМгБІгАБдљЬж•≠жЦЩгАБ5000еЖЖпљЮ10000еЖЖз®ЛеЇ¶гБѓи¶ЪжВЯгБЧгБ¶гБКгБЛгБ™гБДгБ®гБДгБСгБЊгБЫгВУгАВ

гБњгБЯгБДгБ™гАБи≤†гБСжГЬгБЧгБњгВТи®АгВПгБ™гБДгБЯгВБгБЂгВВгАБгБІгБНгВМгБ∞иЗ™еИЖгБІгГИгГ©гВ§гБЧгБ¶йАЪж∞ігБХгБЫгБЯгБДгВВгБЃгБІгБЩгАВ
пЉИдї£гВПгВКгБЂеИ©зФ®гБІгБНгВЛгГИгВ§гГђгБЃзҐЇдњЭгВТгБЊгБЪиАГгБИгБЊгБЧгВЗгБЖгАВж•≠иАЕгБХгВУгВТеСЉгВУгБ†е†іеРИгБІгВВзЫігБРжЭ•гБ¶гБПгВМгВЛ
гБ®гБѓгБЛгБОгВКгБЊгБЫгВУгБЃгБІпЉЙ
гБЊгБЪгАБж∞ійЭҐгБМдљОгБДе†іеРИгБѓгАБгВЂгГГгГЧйГ®еИЖгВТгБКгБКгБЖз®ЛеЇ¶гБѓгАБж∞ігВТињљеК†гБЧгБЊгБЩгАВгБУгБУгБІгВњгГ≥гВѓгБЃгГђгГРгГЉгБІж∞ігВТеЕ•гВМ
гБ™гБДгВИгБЖгБЂгБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБДгАВж∞ігБМеЕ•гВКгБЩгБОгБ¶дЊњеЩ®гБЛгВЙжЇҐгВМгВЛгБКгБЭгВМгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВж∞ігВТж±≤гВУгБ†гГРгВ±гГДгВТж®™гБЂзљЃгБДгБ¶
дљЬж•≠гБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВгВЂгГГгГЧйГ®еИЖгВТж∞ігБЂж≤ИгВБгВЛгБЃгБѓгАБз©Їж∞ЧгБМеЕ•гВЙгБ™гБДгВИгБЖгБЂгБЩгВЛгБЯгВБгБІгАБгБУгВМгБІзЬЯз©ЇгГЭгГ≥гГЧгБЃгВИгБЖгБЂ
еЉХгБ£еЉµгВЛгБУгБ®гБІгАБгГДгГЮгГ™гБМе∞СгБЧгБЪгБ§жЙЛеЙНгБЂзІїеЛХгБЧгБ¶гБїгБРгВМгБ¶гБДгБНгАБж∞ігБЃйАЪгВЛз≠ЛйБУгБМгБ§гБДгБ¶гАБзЂѓгБЛгВЙжµБгВМгБ¶и°МгБП
жДЯгБШгБІгБЩгАВгБ†гБЛгВЙгАБгВЖгБ£гБПгВКгВ∞гГГгБ®жКЉгБЧиЊЉгВУгБІгАБдЄАж∞ЧгБЂеЉХгБНдЄКгБТгВЛеЛХдљЬгВТгГѓгГ≥гВїгГГгГИгБЂгБЧгБ¶гАБдљХеЫЮгВВгГ™гВЇгГЯгВЂгГЂгБЂ
зє∞гВКињФгБЧгАБгГДгГЮгГ™гБЂжМѓеЛХгВТдЄОгБИгВЛгБУгБ®гБМе§ІеИЗгБІгБЩгАВ
гБУгБЃгБ®гБНгАБгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБЛгВЙжЙЛеЕГгБЂж∞ігБЃжКµжКЧгБМдЉЭгВПгБ£гБ¶гБДгВЛгБЛ絴гБИгБЪгГБгВІгГГгВѓгБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБДгАВ
е°ЮгБМгБ£гБ¶гБДгВЛгГСгВ§гГЧгБЂеѓЊгБЧгБ¶зД°зРЖгВДгВКжКЉгБЧгБЯгВКеЉХгБДгБЯгВКгБЩгВЛгГѓгВ±гБІгБЩгБЛгВЙељУзДґгАБж∞ігБЃжКµжКЧгБМгБВгВЛгГПгВЇгБІгАБ
гБУгВМгБМзД°гБДе†іеРИгАБгВЂгГГгГЧгБЃгВЈгГЉгГЂгГЙгБМгБІгБНгБ¶гБ™гБПгБ¶гАБгВЂгГГгГЧгБ®дЊњеЩ®гБЃгВєгВ≠гГЮгБЂж∞ігБЃжКЬгБСйБУгБМгБВгВЛеПѓиГљжАІгБМ
гБВгВКгБЊгБЩгАВгБУгВМгБІгБѓгАБгГДгГЮгГ™гБЂеКєжЮЬзЪДгБЂеЬІеКЫгВТгБЛгБСгВЙгВМгБ™гБДгБЃгБІгАБгВЂгГГгГЧгБЃдљНзљЃгВТдњЃж≠£гБЧгБЊгБЩгАВ
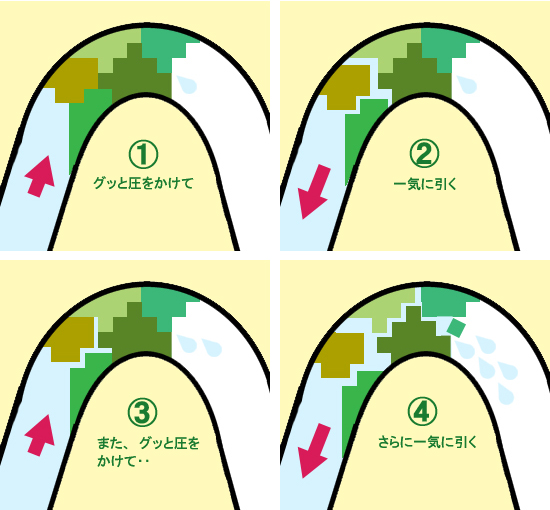
гБЧгБ∞гВЙгБПдљЬж•≠гБЩгВЛгБ®гАБгВігГЬгГГгБ®гБДгБЖйЯ≥гБМгБЧгБ¶гАБж∞ігБМеЉХгБНеІЛгВБгБЊгБЩгАВ
гГРгВ±гГДгБЃж∞ігВТжЇҐгВМгБ™гБДз®ЛеЇ¶гБЂињљеК†гБЧгБ¶гАБж∞ігБМжЩЃйАЪгБЂжµБгВМгБЯгВЙгАБгГДгГЮгГ™гБѓиІ£жґИгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБЭгБУгБІгАБгВҐгГКгВњгБѓгАБгБѓгБШгВБгБ¶гАБж∞іиЈѓгБМйАЪгБШгБЯйБФжИРжДЯгБЂгАБеЦЬгБ≥гВТгБЛгБњгБЧгВБгВЛгБІгБЧгВЗгБЖгАВ
пЉИгБДгВДгАБеИ•гБЂгАБгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгБРгВЙгБДгБІгАБеЦЬгБ≥гВТгБЛгБњгБЧгВБгБ™гБПгБ¶гВВгБДгБДгВУгБІгБЩгБМвА•пЉЙ
жЬАеЊМгБЂгАБгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгВТгГИгВ§гГђгБЂеЄЄеВЩгБЧгБ¶гБКгБПе†іеРИгАБгВДгБѓгВКеЕИзЂѓгБЃгВЂгГГгГЧйГ®еИЖгБМи¶ЛиЛ¶гБЧгБДжДЯгБШгБМгБЧгБЊгБЩгАВ
гБЭгВМгВТдЄКжЙЛгБПйЪ†гБЧгБ¶еПОзіНгБЩгВЛдЄЛзФїеГПгБЃгВИгБЖгБ™еЃєеЩ®гБМжЬАињСгБѓзЩїе†ігБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
жЬАеЊМгБЊгБІи™≠гВУгБІгБПгБ†гБХгБ£гБ¶гБВгВКгБМгБ®гБЖгБФгБЦгБДгБЊгБЧгБЯгАВ


гААгААгАОгВ≥гГ≥гВѓгГ™е£БгГїеЃґеЕЈеЫЇеЃЪ 2 гАП пЉИеѓЭеЃ§гБЃеЇГгВБгБЃгВ≥гГ≥гВѓгГ™е£БгБЂгВѓгГ≠гВЉгГГгГИеЕЉеІњи¶ЛгВТеЫЇеЃЪпЉЙ
гААгААгАОгГРгГЉгГЯгГГгВѓгВєгБЃеЉ±зВєгАП пЉИгГРгГЉгГЯгГГгВѓгВєгБІгВ≥гГЉгГТгГЉи±ЖгВТжМљгБДгБ¶гБДгБЊгБЩгБМвА•пЉЙ
гААгААгАОз™УжЮ†гБЂе∞ПгБХгБ™ж£ЪгВТдљЬгВЛгАП пЉИз™УжЮ†еИ©зФ®гБІ15пљГпљНеєЕгБЃж£ЪгВТдљЬгВЛгБ†гБСгБІдЊњеИ©пЉЙ
гААгААгАОжЬ®гБРгВЛгБњгВ≥гГ≥гВїгГ≥гГИгВњгГГгГЧгАП пЉИгГ™гГУгГ≥гВ∞гБЃеїґйХЈгВњгГГгГЧгБМи¶ЛиЛ¶гБЧгБДгБЃгБІвА•пЉЙ
гААгААгАОжµіжІљгБЃгВ®гГЧгГ≠гГ≥гВТе§ЦгБЩгАП пЉИгГРгВєгГЂгГЉгГ†гБЃгГЛгВ™гВ§гБМж∞ЧгБЂгБ™гВЛжЩВгБѓи¶БгГБгВІгГГгВѓпЉБпЉЙ
гААгААгАОгГХгГ≠гГЉгГ™гГ≥гВ∞гБЃз©ігБЃдњЃеЊ©гАП пЉИDIYгБЃгГПгВ¶гВєгГїгГ°гГ≥гГЖгГКгГ≥гВєгБЃеЃЪзХ™пЉЙ

гААгААж≥®пЉСпЉЙгААгАОгГ©гГРгГЉгВЂгГГгГЧгАПгБѓеТМи£љиЛ±и™ЮгБІгАБиЛ±и™ЮгБІгБЃж≠£еЉПеРНзІ∞гБѓгГЧгГ©гГ≥гВЄгГ£гГЉпЉИPlungerпЉЙгБ®еСЉгБ∞гВМгВЛгАВ
гБЭгБЃдїЦгАБгАОгВЃгГ•гГГгГЭгГ≥гАПгАОгГЬгГ≥гГЖгГ≥гАПгАОгВђгГГгГЭгГ≥гАПгАОгВєгГГгГЭгГ≥гАПгАОгВЇгГГгВ≥гГ≥гАПгАОгГСгГГгВ≥гГ≥гАПгАОгГШгГЧгВЈгАПгБ™гБ©гАБ
еЬ∞жЦєгБЂгВИгБ£гБ¶гАБгБХгБЊгБЦгБЊгБ™еСЉеРНгБМгБВгВЛгАВгАОйАЪж∞ігВЂгГГгГЧгАПгБ®гВВи®АгБЖгАВ