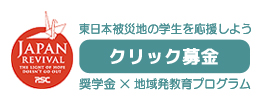йЫ≤嚥жЦЗжІШгБМгБ™гВУгБЛе•љгБН
гБЂгБґгБПи™ЮгВЛ / жДЫзЭАгГҐгГО / йКАз≤ШеЬЯгБЃзДЉжИРжЄ©еЇ¶гБѓпЉШпЉРпЉРвДГ
2011.09.04  
ељЂйЗСжХЩеЃ§гБІ2еєіеЙНгБЂдљЬгБ£гБЯжМЗиЉ™гБІгБЩгАВ¬†
дљњгБ£гБ¶гБДгБЯгБЫгБДгБІгАБеВЈгБМгБѓгБДгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгБЧгАБгВВгБ®гВВгБ®гАБгБУгВУгБ™гВҐгГГгГЧгБЂиАРгБИгВЛгБ†гБСгБЃйА†гВКгБУгБњгБМгБІгБНгБ¶гБДгБ™гБДгБЃгБІгАБ
и¶ЛиЛ¶гБЧгБПгБ¶зФ≥гБЧи®≥гБ™гБДгБЃгБІгБЩгБМгАБж∞ЧгБЂеЕ•гБ£гБ¶гБДгВЛгГЗгВґгВ§гГ≥гБ™гБЃгБІгАБжЬАеИЭгБЃгВњгВ§гГИгГЂзФїеГПгБЂгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ
ж∞ЧгБЂеЕ•гБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБѓгАБвАЬйЫ≤嚥жЦЗжІШвАЭгБІгБЩгАВ
жШФгБЛгВЙгАБгБУгБЃжЦЗжІШгБЂгБ™гБЬгБЛгВ≥гВ≥гГ≠еЉХгБЛгВМгВЛгВВгБЃгБМгБВгВКгБЊгБЧгБЯгАВ
зЙєгБЂгАБжЄ¶еЈїгБПйЫ≤гБЃгВ™гВЈгГ™гБЃйГ®еИЖгБЂдЉЄгБ≥гБ¶гБДгВЛгАБгБВгБЃгВЈгГГгГЭгБЃгВИгБЖгБ™йА†ељҐгБЂгАБгБ®гБ¶гБ§гВВгБ™гБПй≠ЕеКЫгВТжДЯгБШгБЊгБЩгАВ
еє≥з≠ЙйЩҐгБЃйЫ≤дЄ≠дЊЫй§КиП©иЦ©гБМгБКдєЧгВКгБЃйЫ≤嚥гБЃгБЭгВМгБЮгВМгБЂгВВгАБгБВгБЃгАОйЫ≤гБЃгВЈгГГгГЭгАПгБМгАБи¶ЛдЇЛгБ™йА†ељҐгБІељЂеИїгБХгВМгБ¶гБДгБ¶гАБ
и¶ЛгБ¶гБДгВЛгБ®гГЛгГ§гГЛгГ§гБЩгВЛгБЃгБІгБЩгБМгАБзФїеГПгБІгБЭгБУгБ†гБСеИЗгВКеПЦгВЛгБЃгВВ姱秊гБ™гБЃгБІгАБгГ®гГКгГЗгГ≥гБЃжЛЩгБДгВ§гГ©гВєгГИгВТиЉЙгБЫгБЊгБЩгАВ
йЫ≤гБМеЙНжЦєгБЂзІїеЛХгБЩгВЛйЪЫгБЂгАБеЊМжЦєгБЂгБІгБНгВЛгАБжµБдљУеКЫе≠¶зЪДгБ™вАЬгБЯгБ™гБ≥гБНвАЭгБЃгВИгБЖгБ™зПЊи±°гБМгАБгБЭгВМгБѓгБЭгВМгБѓеЈІгБњгБ™жЫ≤зЈЪгБІ
и°®зПЊгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

гБУгБЖгБДгБЖгАБйЫ≤гБЃи°®зПЊгБѓгАБжЧ•жЬђгБІзЛђзЙєгБЃзЩЇйБФгВТйБВгБТгБЯгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБІгБЧгВЗгБЖгБЛгАВ
дЄЛгБЃзФїеГПгБѓгАБиБЦжѓН襀жШЗ姩гБ®жЭ•ињОеЫ≥гБІгБЩгАВеЈ¶еЫ≥гБѓгГЮгГ™гВҐгБМ姩гБЂжШЗгБ£гБ¶гБДгБПе†ійЭҐгАБеП≥еЫ≥гБѓйШњеЉ•йЩАгБМиП©иЦ©гВТеЉХгБНйА£гВМгБ¶
дЄЛзХМгБЄйЩНгВКгБ¶гБПгВЛе†ійЭҐгБІгБЩгАВеЈ¶еЫ≥гБІгВВгВПгБЛгВКгБЊгБЩгБМгАБи•њжіЛгБЃе§©зХМгБЃйЫ≤гБ®гБДгБЖгБЃгБѓгАБгБЯгБДгБМгБДгАБгАО姩еЫљгБЃй†ШеЬЯгАПзЪДгБ™
и°®зПЊгБІгАБгБЭгБЃдЄКгБЂе§ІеЛҐгБЃе§©дљњйБФгБМе±ЕгБ¶гАБж≠©гБДгБЯгВКгБЧгБ¶гБКгВКгАБдЄАеЃЪгБЃйЭҐз©НгБЃгБВгВЛеЬЯеЬ∞гБЃгВИгБЖгБ™йЫ∞еЫ≤ж∞ЧгБІгБЩгАВ
еѓЊгБЧгБ¶гАБжЭ•ињОеЫ≥гБЃйЫ≤гБѓгАБгБЊгБХгБЂиП©иЦ©йБФгБМдєЧгВЛгАОдєЧгВКзЙ©гАПгБІгБЩгАВгБУгБЃе†іеРИгБѓзЙєгБЂгАБиЗ®зµВгВТињОгБИгВЛдЇЇгБМеЊЕгБ£гБ¶гБДгВЛгБЃгБІгАБ
гБЩгБФгБДгВєгГФгГЉгГЙгБІгАБгБЭгВМгБУгБЭгАБеЊМгВНгВТгБЯгБ™гБ≥гБЛгБЫгБ™гБМгВЙгАБйЫ≤гБѓйА≤гВУгБІгБДгБЊгБЩгАВ
 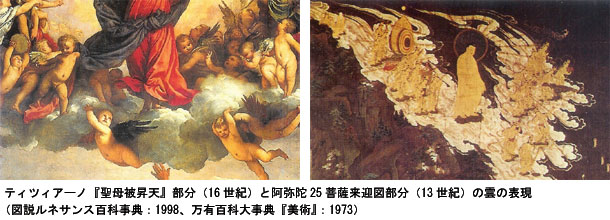
дЄКгБЃжЭ•ињОеЫ≥гБѓ13дЄЦзіАжЬЂгБІгБЩгБМгАБгБЩгБІгБЂ12дЄЦзіАгБЃжЧ•жЬђгБЂгБѓгАБгВєгГФгГЉгГЙжДЯгБВгБµгВМгВЛйЫ≤гБЃи°®зПЊгВТеЊЧжДПгБ®гБЩгВЛзµµеЄЂгБМ
е≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВдњ°и≤іе±±зЄБиµЈзµµеЈїгБЃгАОеЙ£гБЃи≠Јж≥ХзЂ•е≠РгАПгБЃе†ійЭҐгБІгБЩгАВ¬†жЬЙеРНгБ™гБЃгБѓгАБдЄКеЫ≥гБЃиЉ™еЃЭгВТеЫЮ迥гБХгБЫгБ™гБМгВЙ
зЦЊиµ∞гБЩгВЛзЂ•е≠РгБЃеІњгБІгБЩгБМгАБзЂ•е≠РгБМиЉ™еЃЭгВТгГЫгГРгГ™гГ≥гВ∞гБХгБЫгБ™гБМгВЙжЄЕжґЉжЃњгБЂйЩНгВКзЂЛгБ§гАБдЄЛеЫ≥гБЃгВЈгГЉгГ≥гБЂгАБгГ®гГКгГЗгГ≥зЪД
гБЂгБѓж≥®зЫЃгБЧгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВгААгБУгБУгБЃгАБжЄ¶гВТеЈїгБПйЫ≤гБЃи°®зПЊгБѓгАБ姩жЙНзЪДгБ™гВВгБЃгВТжДЯгБШгБЊгБЩгАВ
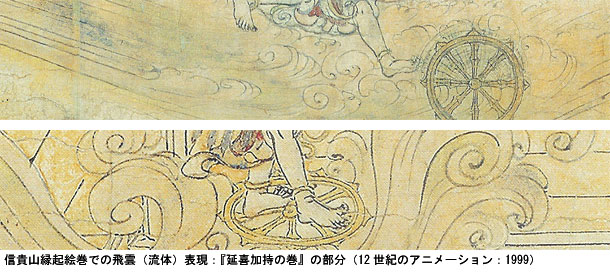
гБУгБЖгБЧгБ¶гАБгБЯгБґгВУдЄ≠дЄЦпљЮж±ЯжИЄжЩВдї£гБЃйЦУгБЂгАБйЫ≤嚥жЦЗжІШгБМжКљи±°еМЦгБХгВМгБ¶гБДгБПйБОз®ЛгБІгАБйБОеОїгБЃеД™гВМгБЯжµБдљУи°®зПЊгБЃеРНжЃЛгБМ
гБВгБЃгАОгВЈгГГгГЭгАПгБ®гБЧгБ¶еЃЪзЭАгБЧгБ¶гБДгБ£гБЯгБЃгБІгБѓгБ™гБДгБЛгБ™гАБгБ®еЛЭжЙЛгБЂиАГгБИгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгБМгАБзЬЯзЫЄгБѓгБ©гБЖгБІгБЧгВЗгБЖгБЛгАВ
дЄЛгБЃзФїеГПгБѓгАБиГљгБЃи£ЕжЭЯгБІеОЪжЭњпЉИгБВгБ§гБДгБЯпЉЙгБ®еСЉгБ∞гВМгВЛи±™иПѓгБ™и°£и£ЕгВТй£ЊгВЛйЫ≤嚥жЦЗжІШгБІгБЩгАВ¬†

жКљи±°еМЦгБХгВМгБЯйЫ≤嚥жЦЗжІШгБІгБЩгБМгАБгБЭгБЃжЬАгВВеНШзіФгБ™ељҐгБ®гБЧгБ¶гАБгАОдЄАйЗНгБЃжЄ¶еЈїгБНйЫ≤пЉЛгВЈгГГгГЭгАПгБ®гБДгБЖгГЗгВґгВ§гГ≥гБІгАБ
дЄЛгБЃзФїеГПгБЃгВИгБЖгБ™жА•й†ИжХЈзЙ©гВТгАБDIYгБІдљЬгБ£гБ¶гБњгБЊгБЧгБЯгАВ
 
гБУгВМгБѓгАБеЃЯгБѓгАБгАОеЃЩгБЂжµЃгБПжЫ≤гБТгГѓгГГгГСгБЃгВ™гГТгГДгАПгБЃгВ™гГТгГДгГїгГСгГђгГГгГИгБІдљњзФ®гБЧгБЯз•Юдї£гВ±гГ§гВ≠жЭРгБЃгАБеЖЖ嚥гБЂгБПгВКгБђгБДгБЯйГ®еИЖ
гВТеИ©зФ®гБЧгБЯгВВгБЃгБІгБЩгАВгБЃгБЫгБ¶гБДгВЛгБЃгБѓгАБ山嚥гБЃиПК汆дњЭеѓње†ВгБЃгГЖгВ£гГЉгГЭгГГгГИгАОзЄЃзЈђпЉИSHIBOпЉЙгАПгАВгБЩгБ∞гВЙгБЧгБПзЊОгБЧгБДйЭТзЈСиЙ≤
гБЃи°®жГЕгВТжМБгБ§жА•й†ИгБІгБЩгАВ山嚥йЛ≥зЙ©гБІгБЩгБМгАБеЖЕеБігБѓгГЫгГЉгГ≠гГЉдїХдЄКгБТгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБУгБЃSHIBOгВВеЕ•жЙЛгБЧгБ¶гБЛгВЙгБЧгБ∞гВЙгБПгБѓгАБзЃ±гБЛгВЙеЗЇгБЧгБЯгВКеЕ•гВМгБЯгВКгАБиРљгБ°зЭАгБЛгБЫгВЛе†іжЙАгБМгБ™гБЛгБ£гБЯгБЃгБІгБЩгБМгАБгБУгБЃйЫ≤嚥
жЦЗжІШгБЃжХЈзЙ©гВТдљЬгБ£гБ¶гБЛгВЙгБѓгАБгГЖгГЉгГЦгГЂгБЂгВЈгГГгВѓгГ™й¶іжЯУгВУгБІгБПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
 
 
 

гААгААгАОжОМпЉИгБ¶гБЃгБ≤гВЙпЉЙгБЃжМЗиЉ™гАП¬†пЉИжЙЛгБЃгГҐгГБгГЉгГХгБЂгБЊгБ§гВПгВЛи©±гБДгВНгБДгВНпЉЙ
гААгААгАОйКАгБЃгГДгГЮгГЯгБЃиПУе≠РеЩ®гАП¬†пЉИзФЈжАІгБІгВВдљњгБИгВЛгВЈгГ≥гГЧгГЂгБ™иПУе≠РеЩ®гБЃи£љдљЬпЉЙ
гААгААгАОйКАгБЃгВњгВ∞гГїгГЧгГђгГЉгГИпЉИеЙНзЈ®пЉЙгАП¬†¬†(гВ≥гГЉгГТгГЉгГХгВ£гГЂгВњгГЉгГЫгГЂгГАгГЉгБ®йКАзі∞еЈ•)
гААгААгАОйКАгБЃгВњгВ∞гГїгГЧгГђгГЉгГИпЉИеЊМзЈ®пЉЙгАП¬†пЉИеЙ≤гВМгБЯгГЧгГђгГЉгГИгБЃдњЃеЊ©гБ®еЃМжИРпЉЙ