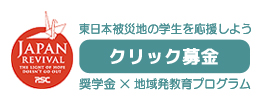жЧ•жЬђгБЃгБКй¶ЩгБІиРљгБ°зЭАгБП
гБКй¶ЩпЉИгВ§гГ≥гВїгГ≥гВєпЉЙгБІж∞ЧжМБгБ°гВТж•љгБЂ / еѓЭеЃ§ / жДЫзЭАгГҐгГО / зОДйЦҐ
2011.10.13 
зФїеГПгБѓзОДйЦҐгБЂзљЃгБДгБ¶гБДгВЛй¶ЩзВЙгБІгБЩгАВж®™гБЃдїПй†≠гБ®гБКгБЭгВНгБДгБЃеП∞еЇІгВТDIYгБІдљЬгВКгБЊгБЧгБЯгАВ
еЃЯгБѓгБУгБЃдїПй†≠гБЃеП≥еБігБЂгВВзљЃзЙ©гБМгБВгБ£гБ¶гАБгБУгБЃеП∞еЇІгБѓдЄЙеєЕеѓЊпЉИгБХгВУгБЈгБПгБ§гБДпЉЙгВТжІЛжИРгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
еП∞еЇІгБЃжЬ®жЭРгБѓгАБ34гГЯгГ™еОЪгБЃвАЭгГСгГЙгГГгВѓвАЭгБЂгБЧгБЊгБЧгБЯгАВгГСгГЙгГГгВѓгБѓгВҐгГХгГ™гВЂеОЯзФ£гБЃгВЂгГ™гГ≥гБЃдї≤йЦУгБІгАБзЊОгБЧгБД赧иЙ≤гБМзЙєеЊігБІгБЩгАВ
еЉЈйЭ≠гБІз°ђгБПиАРдєЕжАІгБЂеД™гВМгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБЛгВЙгВѓгГ©гВЈгГГгВѓгВЃгВњгГЉгБЃеБійЭҐгБ™гБ©гБЂгВВдљњгВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
й¶ЩзВЙгБѓгАБеѓМе±±гБЃйЂШе≤°йКЕеЩ®и£љгБІгАОж≥ҐеНГй≥•гАПгАВйБЇиЈ°гБЛгВЙжОШгВКеЗЇгБЧгБЯгВИгБЖгБ™еП§иЙ≤гБЂйЭҐзЩљгБњгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
жЭ•еЃҐгБЃгБВгВЛ1жЩВйЦУеЙНгБПгВЙгБДгБЂзДЪгБНзµВгБИгВЛжЩВйЦУйЕНеИЖгБІгАБзОДйЦҐгБЃй¶ЩзВЙгБІжЧ•жЬђгБЃгВєгГЖгВ£гГГгВѓзКґгБЃгБКй¶ЩгВТзДЪгБПгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
зДЪгБДгБЯзЫіеЊМгБЂгАБгБКеЃҐжІШгВТињОгБИгБ¶гБЧгБЊгБЖгБ®гАБй¶ЩгВКгБМе∞СгБЧгГПгГГгВ≠гГ™гБЧгБЩгБОгБ¶гАБгБДгБЛгБЂгВВзДЪгБНгБЊгБЧгБЯпЉБгБ£гБ¶жДЯгБШгБЂгБ™гВЛгБЃгБІгАБ
й¶ЩгВКгВТжДЯгБШгВЛгБЛжДЯгБШгБ™гБДз®ЛеЇ¶гБЊгБІжКСгБИгВЛгБЃгБЂгАБ1жЩВйЦУгБїгБ©гБЛгБЛгВЛгБЛгВЙгБІгБЩгАВ
гБУгВМгБМгАБгВ§гГ≥гГЙгБЃгБКй¶ЩгБ†гБ£гБЯгВЙгАБгБУгБЖгБѓгБДгБНгБЊгБЫгВУгАВдЄАйА±йЦУгБПгВЙгБДеЊЕгБЯгБ™гБДгБ®(^ѕЙ^*)
жОІгБИзЫЃгБ™гБКй¶ЩгБЃеЫљгБІиЙѓгБЛгБ£гБЯгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВгБІгВВгАБжЧ•жЬђгБЃгБКй¶ЩгБ†гБСгБІгБѓгБ™гБПгБ¶гАБжђ°еЫЮгБКи©±гБЧгБЩгВЛгГБгГЩгГГгГИгБЃгБКй¶ЩгВВгАБ
гБНгВПгВБгБ¶гВҐгГГгВµгГ™гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБХгБ¶гАБзОДйЦҐгБІзДЪгБПгБКй¶ЩгБІгБЩгБМгАБйОМеАЙгБЃйђЉй†≠姩иЦЂе†ВгБЃгАОиЦЂзР≥гАПгВДжЧ•жЬђй¶ЩйБУгБЃгАОдЉљзЊЕе§Іи¶≥гАПгБЃгВєгГЖгВ£гГГгВѓгГїгВњгВ§гГЧпЉСжЬђгВТ
зБ∞гБЃдЄКгБЂеѓЭгБЛгБЫгБ¶дљњгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБДгБЪгВМгВВдЉљзЊЕз≥їгБЃгБКй¶ЩгБ®и®АгВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
 
гАОдЉљзЊЕз≥їгБЃгБКй¶ЩгБ®и®АгВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАПгБ®жЫЦжШІгБЂи®АгБ£гБЯгБЃгБѓгАБдЉљзЊЕгБЂйЦҐгБЧгБ¶гГ®гГКгГЗгГ≥гБЂгБѓгБ®гБ¶гВВи©ХдЊ°гБѓзД°зРЖгБ†гБЛгВЙгБІгБЩгАВ
дЉљзЊЕпЉИгБНгВГгВЙпЉЙгБ®гБДгБЖеРНеЙНгБЛгВЙгАБгБЭгБЧгБ¶гБЭгБЃжЭ•ж≠ігВТзЯ•гВМгБ∞зЯ•гВЛгБїгБ©гАБй≠ЕдЇЖгБХгВМгВЛгБУгБЃй¶ЩжЭРгБѓгАБжЦЗзМЃгБЂи®ШгБХгВМгБ¶гБЛгВЙгБІгВВ
еНГжХ∞зЩЊеєігБ®гБДгБЖж≠іеП≤гВТеИїгБњгБ™гБМгВЙгАБжЬ™гБ†гБЭгБЃжИР嚥гБЃгГЧгГ≠гВїгВєгБМеЃМеЕ®гБЂгБѓжШОгВЙгБЛгБЂгБХгВМгБ¶гБДгБ™гБДиђОгВБгБДгБЯгВЈгГ≠гГҐгГОгБІгБЩгАВ
жЭ±еНЧгВҐгВЄгВҐгБЂгБКгБДгБ¶гВЄгГ≥гГБгГІгВ¶гВ≤зІСгБЃж§НзЙ©гБМгБВгВЛз®ЃгБЃгГРгВѓгГЖгГ™гВҐгБЃдљЬзФ®гБЂгВИгБ£гБ¶ж®єиДВеМЦгБЧгБ¶ељҐжИРгБХгВМгВЛгВЙгБЧгБДж≤Ий¶Щ
пЉИгБШгВУгБУгБЖпЉЙгБ®гБДгБЖй¶ЩжЭРгБЃдЄ≠гБЛгВЙгАБгБХгВЙгБЂдљХгВЙгБЛгБЃжЭ°дїґгБЂгВИгВКгАБгБЯгБРгБДз®АгБ™иК≥й¶ЩгВТйЪ†гБЧжМБгБ§йАЄжЭРгБ®гБЧгБ¶и¶ЛеЗЇгБХгВМгВЛдЉљзЊЕгБѓгАБ
зПЊеЬ®гГѓгВЈгГ≥гГИгГ≥жЭ°зіДгБЂгВИгБ£гБ¶дњЭи≠ЈгБХгВМгБ¶гБКгВКгАБи°®зЂЛгБ£гБ¶гБѓжµБйАЪгБМж≠ҐгБЊгБ£гБ¶гБДгВЛзКґжЕЛгБІгБЩгАВ
жЧ•жЬђгБЃиАБиИЧй¶ЩеПЄгБѓйХЈеєігБЃйЦУгВєгГИгГГгВѓгБЧгБ¶гБНгБЯгБЯгВБгАБдЉљзЊЕгВТжЭРжЦЩгБ®гБЧгБ¶дїКгВВгБКй¶ЩгВТдљЬгВКзґЪгБСгВЛгБУгБ®гБМеПѓиГљгБ™гВИгБЖгБІгБЩгБМгАБ
йЂШдЊ°гБ™гВВгБЃгБЂгБ™гВЛгБ®жХ∞еНБдЄЗгБѓжЩЃйАЪгАБй¶ЩйБУгБЂдљњгВПгВМгВЛй¶ЩжЬ®гБЃдЉљзЊЕгБІеРНгБЃзЯ•гВМгБЯгГҐгГОгБЂгБ™гВЛгБ®жХ∞гВ∞гГ©гГ†гБІзЫЃгБЃзОЙгБМ
й£ЫгБ≥еЗЇгВЛгВИгБЖгБ™дЊ°ж†ЉгБЂгБ™гВЛгБ®иБЮгБНгБЊгБЩгАВ
гГ®гГКгГЗгГ≥гБМдЉљзЊЕгБ®гБЧгБ¶вАЬиБЮгБДгБ¶вАЭгБНгБЯй¶ЩгВКгБЃзµМй®УгБ™гБ©гБЯгБЛгБМзЯ•гВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВжЩЃйАЪгБЂдЉљзЊЕз≥їгБЃй¶ЩгВКгБ®гБХгВМгВЛгВВгБЃгБЃдЄ≠гБЂгАБ
жЬђжЭ•гБЃе§©зДґдЉљзЊЕгБЃиК≥й¶ЩгБМгБ©гВМгБПгВЙгБДгБЃеЙ≤еРИгБІеПНжШ†гБХгВМгБ¶гБДгВЛгБЛгБ™гВУгБ¶иЙ≤гВУгБ™жДПеС≥гБІжАЦгБПгБ¶и©ХдЊ°гБІгБНгБЊгБЫгВУгАВ
гБ®гБЂгБЛгБПгАБгБЭгБЖгБДгБЖгВ¶гГ≥гГБгВѓзЪДгБ™гБУгБ†гВПгВКгВТжН®гБ¶гБ¶иЗ™еИЖгБМж∞ЧжМБгБ°иЙѓгБПгБ™гВЛгБКй¶ЩгВТжОҐгБЫгБ∞гБДгБДгБЃгБІгБЩгАВ
йђЉй†≠姩иЦЂе†ВгБЃгАОиЦЂзР≥гАПгБѓгАБж∞ЧжМБгБ°гБЃгБДгБДиПѓгВДгБЛгБ™йЫ∞еЫ≤ж∞ЧгБЃй¶ЩгВКгБМжЃЛгВКгБЊгБЩгАВйђЉй†≠姩иЦЂе†ВгБѓдЉљзЊЕз≥їгБЃй¶ЩгВКгБ®гБЧгБ¶гАБ
гВВгБЖдЄАгБ§гАОиАБжЭЊгАПгВТеЗЇгБЧгБ¶гБКгВКгАБгБЭгБ°гВЙгВТи©ХдЊ°гБЩгВЛдЇЇгВВе§ЪгБДгБЃгБІгБЩгБМгАБгБ™гБЬгБЛгАОиАБжЭЊгАПгБЃжЮѓгВМгБЯйЫ∞еЫ≤ж∞ЧгБМиЛ¶жЙЛгБІгАБ
гАОиЦЂзР≥гАПгВДгАОдЉљзЊЕе§Іи¶≥гАПгБЃжЦєгБМгГ™гГ©гГГгВѓгВєгБІгБНгВЛгБЃгБІгБЩгАВ
гАОдЉљзЊЕе§Іи¶≥гАПгБЃжЧ•жЬђй¶Ще†ВгБѓгАБдЄАиИђгБЂгБѓгАБвАЬйЭТйЫ≤вАЭгБЃгВИгБЖгБ™вАЬдїПе£ЗзФ®гБЃгБКзЈЪй¶ЩвАЭгБІжЬЙеРНгБІгБЩгБМгАБй¶ЩйБУгБЃгБКй¶ЩгВДжµЈе§Цз≥ї
гВ§гГ≥гВїгГ≥гВєгБЂгВВеЃЯеКЫгБМгБВгВКгАБгБКй¶ЩгБЃеИЖйЗОгБІгВ∞гГЂгГЉгГЧгБ®гБЧгБ¶е§ІгБНгБ™е≠ШеЬ®гБІгБЩгАВгБХгБНгБїгБ©гБЃйђЉй†≠姩иЦЂе†ВгВДйКАеЇІй¶ЩеНБгАБ
гГХгГ©гГ≥гВєгБЃгВ®гВєгГЖгГРгГ≥гБ™гБ©гВВйЦҐйА£дЉЪз§ЊгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гБХгБ¶гАБгБУгБ°гВЙгБЃзФїеГПгБѓеѓЭеЃ§зФ®гБЃе∞ПеЮЛй¶ЩзВЙгБІгБЩгАВ

еП∞еЇІгБѓгАБгАОеЃЩгБЂжµЃгБПжЫ≤гБТгГѓгГГгГСгБЃгВ™гГТгГДгАПгБІзієдїЛгБЧгБЯгВ™гГТгГДгГїгГСгГђгГГгГИгБ®гБКгБ™гБШгБПз•Юдї£гВ±гГ§гВ≠гБІдљЬгВКгБЊгБЧгБЯгАВ
й¶ЩзВЙгБѓдєЭи∞ЈзДЉгБЃгАОйЭТз≤ТйЙДдїЩгАПпЉИгАОйЭТз≤ТгАПгБѓгАОгБВгБКгБ°гБґгАПгБ®и™≠гБњгБЊгБЩпЉЙгАВгБЛгВПгБДгБДгБСгВМгБ©еУБгБЃгБВгВЛдљЗгБЊгБДгБІгАБ
еѓЭеЃ§гБЃз©Їж∞ЧгБМжЈАгВУгБІгБДгВЛгБ™жДЯгБШгБЯжЩВгБЂгАБгБ°гВЗгБ£гБ®еПЦгВКеЗЇгБЧгБ¶зЯ≠жЩВйЦУгБКй¶ЩгВТзДЪгБПгБЃгБЂгГФгГГгВњгГ™гБЃе§ІгБНгБХгБІгБЩгАВ
дЄНжАЭи≠∞гБ™гБУгБ®гБЂгАБгГ®гГКгГЗгГ≥гБМеѓЭеЃ§гБЂењЕи¶БгБ†гБ®жАЭгБЖй¶ЩгВКгБѓгАБгГ™гГУгГ≥гВ∞гВДзОДйЦҐгБІйБЄгБґй¶ЩгВКгБ®гБѓгБЊгБ£гБЯгБПйБХгБДгБЊгБЩгАВ
гБУгВМгБѓйАЖгБЂгАБиЙ≤гАЕгБ™жЦєгБЂиБЮгБДгБ¶гБњгБЯгБДгБПгВЙгБДгБІгБЩгАВгВҐгГКгВњгБѓгАБгБФиЗ™еИЖгБЃеѓЭеЃ§гБЂгАБгБ©гВУгБ™й¶ЩгВКгВТйБЄгБ≥гБЊгБЩгБЛпЉЯ
гБЛгБ™гВКгБЃи©¶и°Мй̃虧гБЃзµРжЮЬгАБзПЊеЬ®гБЪгБ£гБ®дљњгБ£гБ¶гБДгВЛеѓЭеЃ§зФ®гБЃгБКй¶ЩгБѓгАБгБУгВМгВВжЧ•жЬђй¶Ще†ВгБЃ
пљЖпљНпЉИгГХгГђгВ∞гГ©гГ≥гВєгГїгГ°гГҐгГ™гГЉпЉЙгБ®гБДгБЖгВЈгГ™гГЉгВЇгБЃгАОгГЮгВ¶гГ≥гГЖгГ≥гГїгГЦгГђгВєгАПгБІгБЩгАВ

гВµгВ§гГЧгГђгВєгАБгГ°гВ§гГЧгГЂгАБгГЪгГСгГЉгГЯгГ≥гГИгБМгВ≠гГЉгГОгГЉгГИгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБЛгВЙеИ§гВЛгВИгБЖгБЂгАБж£ЃжЮЧз≥їгБЃй¶ЩгВКгБІгБЩгАВ
гБУгВМгБМгБЩгБФгБПиРљгБ°зЭАгБДгБ¶гАБйЦЙгБЦгБХгВМгБЯеѓЭеЃ§гБІй¶ЩгВТзДЪгБДгБЯгВКгБЩгВЛгБ®жЬђжЭ•зЕЩгБЯгБДгБѓгБЪгБ™гВУгБІгБЩгБМгАБгБ™гБЬгБЛжЈ±еСЉеРЄгВТ
гБЧгБЯгБПгБ™гВЛгВИгБЖгБ™зИљгВДгБЛгБ™ж∞ЧеИЖгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
ж£ЃжЮЧз≥їгБ™гВЙгАБеРМгБШпљЖпљНгВЈгГ™гГЉгВЇгБЃдЄ≠гБЂгАОгГђгВ§гГ≥гГХгВ©гГђгВєгГИгАПгБ®гБДгБЖгБЭгБЃгВВгБЃгВЇгГРгГ™гБЃеРНеЙНгБЃгБКй¶ЩгБМгБВгВЛгБЃгБІгБЩгБМгАБ
гБУгВМгБМгБЊгБЯгАБеЕ®зДґеРИгВПгБ™гБДвА¶гАВй¶ЩгВКгБЃе•љгБНеЂМгБДгБ®гБДгБЖгБЃгБѓгАБгБїгВУгБ®гБЖгБЂдЄНжАЭи≠∞гБІгБЩгАВ
 
 
 
 
 

гААгААгАОзБ∞гВТгВ≠гГђгВ§гБЂгБЧгБ¶иРљгБ°зЭАгБПгАПгААпЉИгГБгГЩгГГгГИй¶ЩгГїдє≥й¶ЩгГїжЧ•жЬђгБЃгБКй¶ЩгБ™гБ©гАБзБ∞гБЃдЄКгБІзДЪгБПй¶ЩгВКгБЃж•љгБЧгБњпЉЙ
гААгААгАОйЫ≤嚥жЦЗжІШгБМгБ™гВУгБЛе•љгБНгАП¬† пЉИйЫ≤嚥жЦЗжІШгБЂгБЊгБ§гВПгВЛи©±гБДгВНгБДгВНпЉЙ
гААгААгАОжОМпЉИгБ¶гБЃгБ≤гВЙпЉЙгБЃжМЗиЉ™гАП¬†пЉИжЙЛгБЃгГҐгГБгГЉгГХгБЂгБЊгБ§гВПгВЛи©±гБДгВНгБДгВНпЉЙ
гААгААгАОйКАгБЃгГДгГЮгГЯгБЃиПУе≠РеЩ®гАП¬†пЉИзФЈжАІгБІгВВдљњгБИгВЛгВЈгГ≥гГЧгГЂгБ™иПУе≠РеЩ®гБЃи£љдљЬпЉЙ
гААгААгАОдЄ≠дЄЦ饮гБЃжЫЄи¶ЛеП∞гВТдљЬгВЛгАП пЉИгГ™гГУгГ≥гВ∞гБЂй£ЊгВЛдЄ≠дЄЦгБЃзЊОи°УжЫЄгБЃе±Хз§ЇеП∞гВВеЕЉгБ≠гВЛжЫЄи¶ЛеП∞пЉЙ¬†